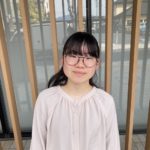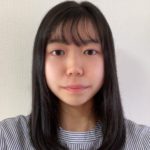鈴木 寛 元文部科学副大臣、東京大学教授、慶應義塾大学特任教授
 「アートマイルで明日の世界を創る人材を!」 2030年頃には多くの仕事が人工知能に置き換わっているでしょう。このような時代に人工知能では代替できない仕事、人間にしかできない仕事は何か?これから未来を創る人に必要とされる力は、違う文化背景を持った人達と協働して問題を解決する力であり、違う能力を持った人達と協働して無から有を生み出す力です。アートマイルは学校でこうした力をつけることができる革新的な学習プログラムです。アートマイルを通して明日の世界を創る人材が育つことを期待しています。
「アートマイルで明日の世界を創る人材を!」 2030年頃には多くの仕事が人工知能に置き換わっているでしょう。このような時代に人工知能では代替できない仕事、人間にしかできない仕事は何か?これから未来を創る人に必要とされる力は、違う文化背景を持った人達と協働して問題を解決する力であり、違う能力を持った人達と協働して無から有を生み出す力です。アートマイルは学校でこうした力をつけることができる革新的な学習プログラムです。アートマイルを通して明日の世界を創る人材が育つことを期待しています。
田村 学 國學院大學教授、元文部科学省視学官
 「グローバルな社会における子どもの学びを世界とつなぐ取組」 日本国内の出来事が即座に世界に発信されるように、世界の出来事も瞬時に私たちの手元に飛び込んできます。地球上の距離はどんどん縮まり、それぞれのつながりや関係が深く密接になってきています。アートマイルは、そんなグローバルな社会における子どもの学びを世界とつなぐ取組です。新しい時代には、豊かな感覚と広い視野が求められます。次世代の子どもの成長を支えるアートマイルに、みんなで参加しましょう。
「グローバルな社会における子どもの学びを世界とつなぐ取組」 日本国内の出来事が即座に世界に発信されるように、世界の出来事も瞬時に私たちの手元に飛び込んできます。地球上の距離はどんどん縮まり、それぞれのつながりや関係が深く密接になってきています。アートマイルは、そんなグローバルな社会における子どもの学びを世界とつなぐ取組です。新しい時代には、豊かな感覚と広い視野が求められます。次世代の子どもの成長を支えるアートマイルに、みんなで参加しましょう。
■教師の言葉 →こちら
■生徒の言葉 →こちら